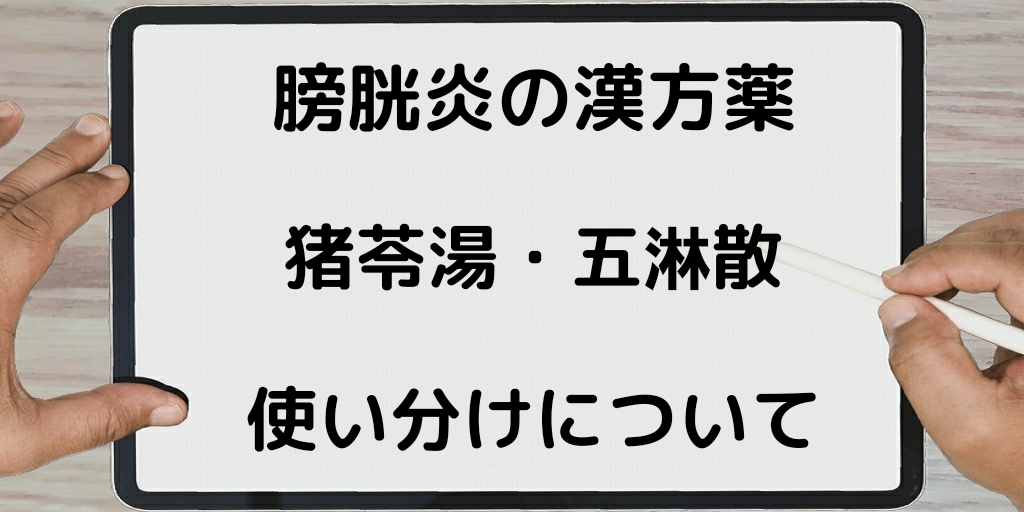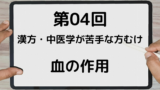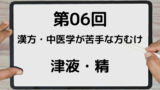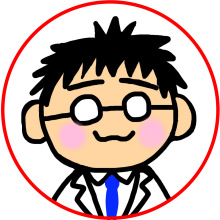
こんにちは!
くくたる(twitterはコチラ)です!
【薬剤師歴11年目】
●フリーランス薬剤師
●管理薬剤師歴:調剤3年、OTC1年目
●1人薬剤師歴(調剤):2年
【漢方薬・ハーブの資格】
●国際中医師
●ハーバルセラピスト
●シニアハーバルセラピスト
※国際中医師は医師免許ではありません。
「膀胱炎の薬はありますか?」
調剤併設型の薬局やドラッグストアだと、そこそこの頻度で相談されますよね?
そんな時、市販の薬では漢方薬を紹介すると思いますが、しっかりとした使い分けの基準はご存じでしょうか?
今回は膀胱炎の漢方薬の使い分けだけでなく、症状によっては受診をしていただく必要もあるため、紹介をしたいと思います!
膀胱炎の状態を中医学で考えると?
中医学では、
①炎症=熱
※細菌感染による炎症も同じく熱
②出血=血熱
③体に水分が溜まる=湿
①~③より、膀胱に水分が溜まり、炎症が起きている状態を
膀胱湿熱(ぼうこうしつねつ)
と表現して考えられております!
猪苓湯(ちょれいとう)とは?
構成生薬
猪苓(チョレイ)、茯苓(ブクリョウ)、沢瀉(タクシャ)、阿膠(アキョウ)、滑石(カッセキ)
生薬の特徴
●利水を行う猪苓がメイン!
利水は水分代謝を改善する作用のことで、膀胱炎の排尿障害を改善して尿排泄を促進します!
※茯苓、沢瀉、滑石も利水作用があります!
※排尿により菌(炎症の元)を外に出すため、清熱作用もあると考えられております!
各生薬の水の巡らせ方については下記記事を参考にしていただけると助かります!
●補血、滋陰、止血作用のある阿膠!
補血は血(けつ)の補給、滋陰は陰液の補給を意味します!
※陰液=血、津液を併せたもの
猪苓湯の効能・効果(市販薬)
体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症:排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ
五淋散(ごりんさん)とは?
構成生薬
茯苓(ブクリョウ)、芍薬(シャクヤク)、木通(モクツウ)、当帰(トウキ)、山梔子(サンシシ)、滑石(カッセキ)、黄芩(オウゴン)、地黄(ジオウ)、車前子(シャゼンシ)、甘草(カンゾウ)、沢瀉(タクシャ)
生薬の特徴
●清熱する山梔子がメイン!
炎症による排尿痛、尿のにごり、尿が濃くなる、血尿なども熱症状と考えます!
※黄芩も清熱作用があります!
※炎症を鎮めるだけでなく、抗菌も期待できます!
●利水作用のある生薬!
茯苓、沢瀉、車前子、滑石、木通
※排尿により菌(炎症=熱)を外に出すため、清熱作用もあると考えられております!(茯苓以外)
●補血作用のある生薬!
地黄、当帰、芍薬
熱が続くことで陰(血や津液)が消耗してしまうため、補う作用のある生薬が含まれております!
五淋散の効能・効果(市販薬)
体力中等度のものの次の諸症:
排尿痛、頻尿、残尿感、尿のにごり
猪苓湯と五淋散の特徴まとめ
猪苓湯の特徴
●膀胱湿熱のうち、利水をメインとしている! 清熱作用もあり!
※残尿感やむくみ、喉の渇きなど水分代謝異常がメイン!
五淋散の特徴
●膀胱湿熱のうち、清熱をメインとしている! 利水作用もあり!
※排尿痛や尿が濃くなる、尿がにごる、血尿などの熱症状(炎症)がメイン!
市販で対応してはいけない状況とは?
①発熱
②腰痛
これらの症状がある場合は、膀胱炎ではなく腎臓の炎症である可能性が高いので、市販薬で応対するのではなく受診をしていただく必要があります!!
気軽に大丈夫だろう…は禁物です!!
最後に
というわけで、今回は膀胱炎で使用される猪苓湯と五淋散の使い分けについて紹介しました!
適切な治療ができるよう、市販薬の紹介だけでなく受診勧奨の可能性も考慮して応対していきたいですね!
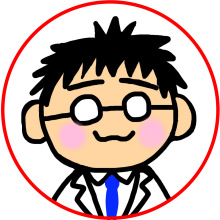
.png)