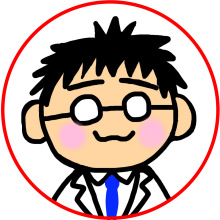
こんにちは!
くくたる(twitterはコチラ)です!
【薬剤師歴11年目】
●フリーランス薬剤師
●管理薬剤師歴:調剤3年、OTC1年目
●1人薬剤師歴(調剤):2年
【漢方薬・ハーブの資格】
●国際中医師
●ハーバルセラピスト
●シニアハーバルセラピスト
※国際中医師は医師免許ではありません。
今回は消風散(しょうふうさん)という痒みを抑える漢方薬と、中医学での痒みについての考え方について紹介したいと思います!
中医学でいう痒みの定義
風邪(ふうじゃ)とは?
痒みの原因は風邪(ふうじゃ)と考えられております!
風が皮膚表面を刺激して、痒みが生じるイメージですね!
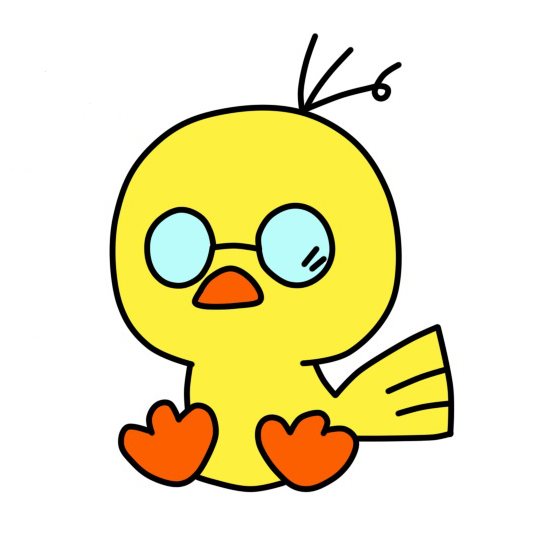
耳の穴にフーっと息を吹きかけるとこそばゆい、あの感じがイメージしやすいでしょうか?
正直なところ私は最初、うさんくさいなと思ってしまいました…。
ただそれでは先に進まないので、
中医学では風邪(ふうじゃ)というものが原因と考えられているんだなと受け入れて勉強しました!
風邪(ふうじゃ)と他の邪の組み合わせ
風邪は他の邪と合わさる場合が多い点も特徴です!
【風熱】
風邪+熱邪の組み合わせです!
温まることで痒みが増したり、赤みが強い、細菌感染している場合など、熱邪の特徴も併せ持つ状態です!
熱証が長引くと皮膚の乾燥にも繋がります!
【風寒】
風邪+寒邪の組み合わせです!
冷えることで痒みが増す場合など、寒邪の特徴も併せ持つ状態です!
【風湿】
風邪+湿邪の組み合わせです!
水疱やジュクジュクしている場合など、湿邪の特徴も併せ持つ状態です!
ジュクジュクして膿んでいる場合には細菌感染(湿邪+熱邪)の場合も考えられます!
【風燥】
風邪+燥邪の組み合わせです!
乾燥肌で痒みがある場合など、燥邪の特徴も併せ持つ状態です!
熱証が続くことで乾燥することもあります!
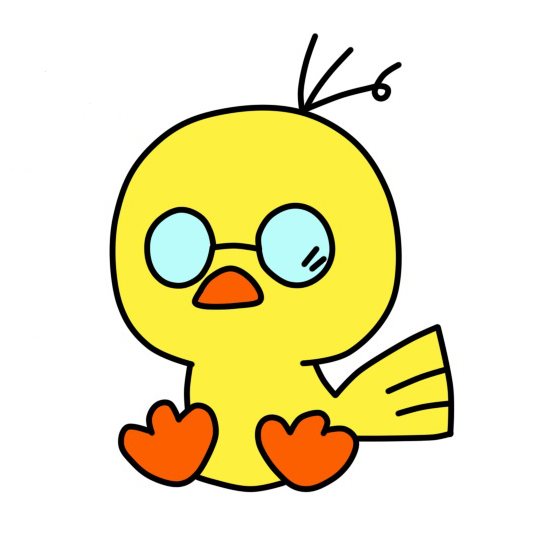
痒みは風邪ですが、
温まると痒くなる、冷えると痒くなる、水疱がある、乾燥肌で痒いなど
風邪以外の邪も影響している場合が多いと覚えておくと良いと思います!
※風邪(ふうじゃ)など6つの邪(六淫)についてまとめた記事はコチラ!
消風散(しょうふうさん)とは?
消風散は疏散外風剤に分類されます!
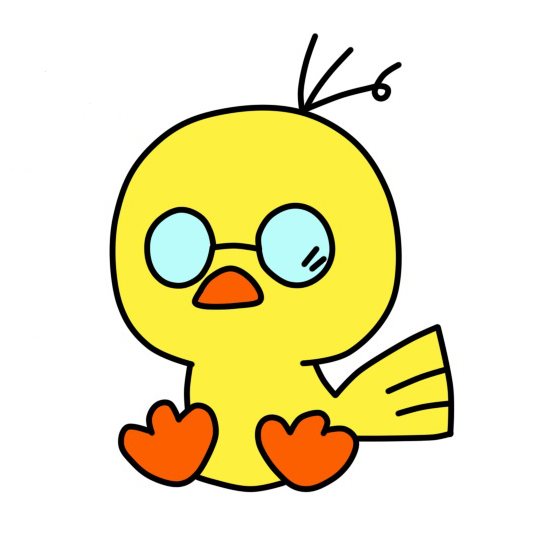
読んで字のごとく、
風を消す=痒みを消す
漢方薬ですね!
生薬構成やどのような痒みを改善するかは下記で紹介します!
消風散の構成生薬
当帰(トウキ)、地黄(ジオウ)、蒼朮(ソウジュツ)、石膏(セッコウ)、木通(モクツウ)、防風(ボウフウ)、牛蒡子(ゴボウシ)、知母(チモ)、胡麻(ゴマ)、甘草(カンゾウ)、蝉退(センタイ)、苦参(クジン)、荊芥(ケイガイ)
生薬の特徴
●風邪を散らす生薬:防風、荊芥、蝉退、牛蒡子
細かな分類は置いておき、こちらの4つの生薬が消風散における痒みを抑える要の生薬です!
※辛温解表薬に分類:防風、荊芥
※辛涼解表薬に分類:蝉退、牛蒡子
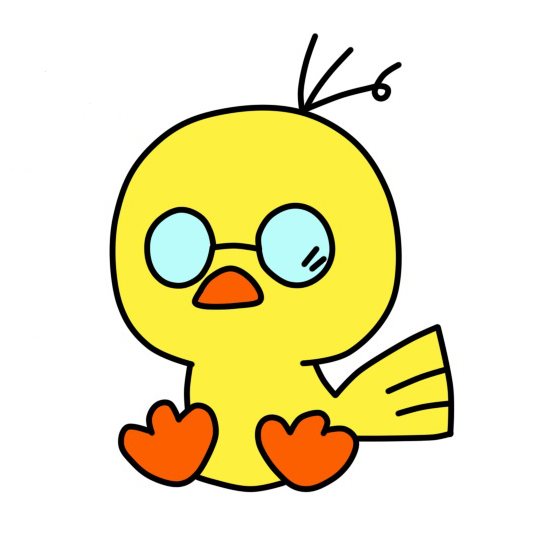
風邪を散らすと表現しておりますが、
風邪を改善する=痒みを改善する
という意味ですね!
解表薬は表の邪を発散させる効果があり、風邪は表に付着するため、
解表薬の中には風邪を散らす効果のある生薬が多数あります!
●清熱作用のある生薬:石膏、知母、苦参
清熱は熱を冷ますという意味です!
熱があると起こる症状:炎症、赤み、温まると痒みが強くなるなど。
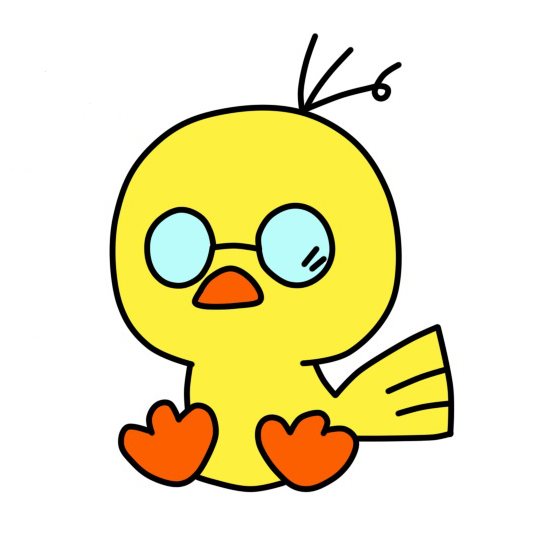
知母については滋陰作用(陰液を補う作用)があり、皮膚乾燥の改善にも関与します!
潤いを与え、熱を冷ますイメージです!
●利水作用のある生薬:木通、蒼朮
水分代謝を改善し、湿潤状態を改善します!
●皮膚に栄養を与える生薬:当帰、地黄、胡麻、知母
皮膚に栄養・潤いを与えることで皮膚の痒みを改善します!
栄養と大雑把に表現しましたが、血や陰液を補うという意味です!
●陰液の補給→乾燥を改善+熱を冷ます→乾燥・炎症を和らげる
●血の補給→皮膚に栄養を与える
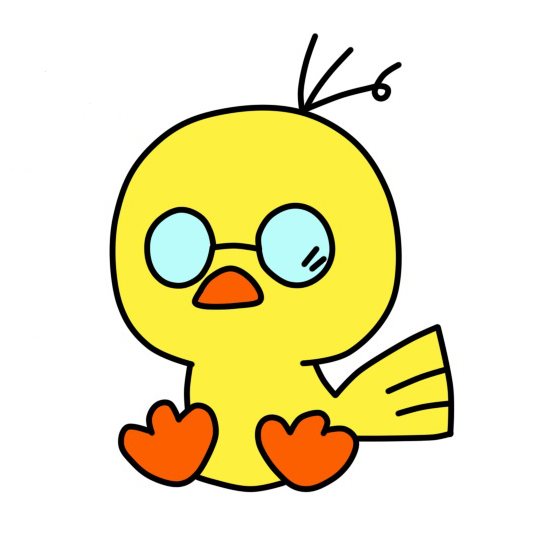
消風散をまとめると、
①皮膚の痒み・炎症をとる!
②皮膚の湿潤状態の改善!
③皮膚に栄養・潤いを与える!
このようなイメージです!
消風散の効能・効果(市販薬)
体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症:湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも
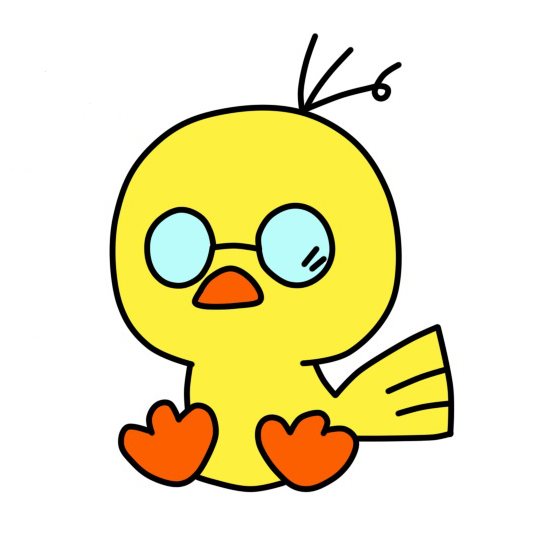
なんとなくイメージがつかめましたか?
消風散をどう説明するか?
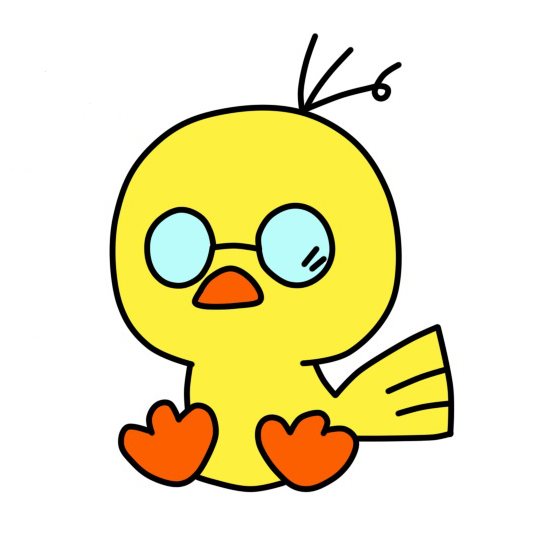
消風散は皮膚の痒みを抑えるお薬です!
また、赤みや湿潤性のある状態を抑え、皮膚に栄養を与えることを同時に行える点が特徴です!
最後に
というわけで、消風散と中医学の痒みの定義についてでした!
皮膚疾患に使用できる他の記事はコチラ↓
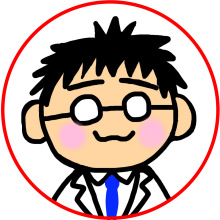
.png)
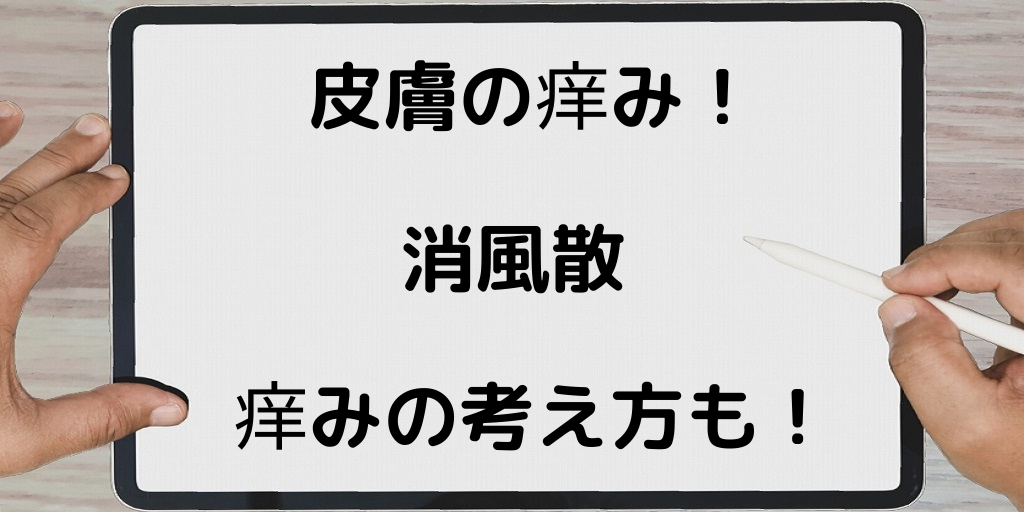

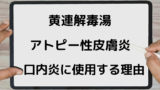
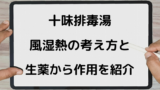
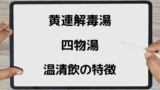
コメント